※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:pcオーディオの過大評価「じじいのぼやき」)
pcオーディオの過大評価「じじいのぼやき」
このQ&Aのポイント
PCオーディオの評価について、高級なオーディオ機器にはかなわないと感じています。
PC内のノイズが音質に影響を与えることや、CPUの動作がジッターを引き起こすことを解説しています。
バッテリーは高音質と思われますが、実はPCには不向きであり、リッピングソフトやデータ保存によっても音質が変わることを述べています。
16bitより24bitなど、まるでデジカメの画素数神話みたいですね、
以下はとあるブログより抜粋した記事ですが、私も色々とPCオーディオをかじりましたが、「高級なオーディオ機器にはかなわんな」という感じです。今、CDはパソコンで製作されるのだから、悪い訳ないと申しますが、なんでもそうですが、実際、自分で試してからものを言ってもらいたいです。
CPUはPC内で最も消費電力の大きいデバイスであり、電流の起きるところには必ずノイズが発生します。ノイズというと空中を伝わる高周波ノイズや電源ラインからのノイズをまっ先に思い浮かべるのですが、実はPC内の最大のノイズとはデバイスが動作することによって発生する電源ノイズです。金井氏によると、外来の飛びつきノイズはエネルギーを持たないため減衰も早いのですが、デバイスの動作によって電源とグラウンドに生じるノイズはエネルギー量が大きく、減衰することなく基板上のさまざまな場所に伝播し、インピーダンスが変化するところ反射して跳ね返り、さまざまなタイミングでクロックを揺らす厄介な存在だそうです。基板パターンの引き回し方によっても音が変わると言われるのは、こういうことも原因です。ここまでくると奥が深いですね。
その程度のことで影響を受けるシステムこそが問題であるといっても、影響を受けないシステムなど現実には存在しません。まして、オーディオ機器として設計されていないPCで、そのようなことが考慮されているはずもありません。300万円もするような機器であれば、設計段階から対策が幾重にも採られているでしょうが、それでも影響をゼロにすることは不可能です。
ALIXを例にあげると、UBSの送り出しのクロックを制御しているのは、サウスブリッジの48MHzの発振器(基板上のY4)です。この発振器はCPUと電源ラインもグラウンドラインも繋がっていますから、その影響をもろに受けます。
さらにCPUが電流を消費すると、ノイズだけでなく当然のことながら基準電位(グラウンド電位)も影響を受けます。CPUの動作は、急激な電源負荷の変化を引き起こす典型的なものだからです。
PCオーディオではノイズ面で有利だという理由でバッテリーが高音質であると思われている節がありますが、実はバッテリーはPCには不向きです。化学変化により電源を供給するバッテリーは内部抵抗が高く、電源負荷の急変動に追従できません。したがって、CPUの急激な負荷変動に追従できず、基準電位のふらつきが大きくなって、Beyond Bit-perfect にあるようにジッターが増えることは容易に想像がつきます。ジッターが増えて丸くなった音を、ノイズがなくなって音がよくなったと感じる人が多いであろうことも、また容易に想像がつきます。実際に比較してみると、出川式電源などのほうが高音質です。
その他でCPUが関係しそうなのは、リッピングソフトでしょう。ソフトウェアによってCPUの挙動が異なるのは当然のことですから、それによるノイズパターンの違いが、HDDにデータが保存されるときにクセとなって残ります。さらにWAVと一口に言ってもいろいろとバリエーションがあるようですから、ソフトウェアによってファイルのPCMデータ以外の部分も異なってきます。リッピングドライブによって音が異なるのは、ドライブによって読み取り時のノイズが異なるからです。
ちなみに、CDからデータを読み取るときのノイズは、HDDからデータを読み取るときのノイズよりも桁外れに大きいそうで、これがファイル再生が有利である本当の理由です。その意味でもディスク再生にはもはや存在意義はなくなっています。「PCオーディオ」や「ネットワークオーディオ」という言葉もそのうち死語になって、ただの「オーディオ」になるかもしれません。そうなったら、このサイトもただの「オーディオ実験室」ですね(笑)。
話をAIFFとWAVに戻すと、どちらもtopコマンドではCPUの負荷に違いはないようですから、ジッターの量を測定したとしてもそんなに差は出ないことが予想されます。
ところが、ジッターというのは量(振幅の大きさ)だけでなく、周波数、スペクトラム(分布のパターン)といった要素で認識する必要があり、この中でも分布のパターンが重要なのだそうです。量的には同じであってもパターンが異なれば音も違ってきます。AIFFとWAVの場合では、どちらが好ましいか意見が別れるようですが、ジッターも最終的にはその人好みのパターンみたいなものに行き着いてしまうようです。
ジッターがあまり少なくなるとかえってつまらない音に聴こえることもあるようで、多少ジッターがあったほうが人によっては好ましく感じることもあるといったことをFIDELIXの中川氏も指摘しています。ジッターによって変調された音の方が好まれるというのは、いかにもオーディオ的な話です。
人によっては強力なCPUを使ったほうが力強い音がするといって、わざわざクアッドコアのCPUでゲーム機ばりのハイパワーマシンを組む人もいるようですが、これなどはジッターの多寡よりも、強力なCPUと電源が生み出すジッターのパターンがその人のお気に入りなのでしょう。
結局のところ、デジタルオーディオで音が変わることの原因といえば、ジッターの問題に集約されるわけですが、ジッターに影響を与えるものといえば、ほとんどあらゆるものが該当します。もちろんほとんど違いが聴き取れないようなものもあるわけですが、原理としては何を変えても音は変わる(ジッターは変わる)と理解しておいたほうが現実的です。実体験が大切なことは否定しませんが、正しい原理を理解しないまま体験だけを重ねても、謎は深まるばかりという結果になるのが関の山です。実際に違いが分かるかどうかは、スピーカーの過渡特性なども大きく影響します。もともと丸い音しかでない低能率のスピーカーでは微妙な変化はわかりにくいと思います。
ジッターについての正しい認識が広まれば、いささか不幸な状況にある現状のデジタルオーディオをめぐる議論も、もっと前向きな方向へと変わっていくはずです。














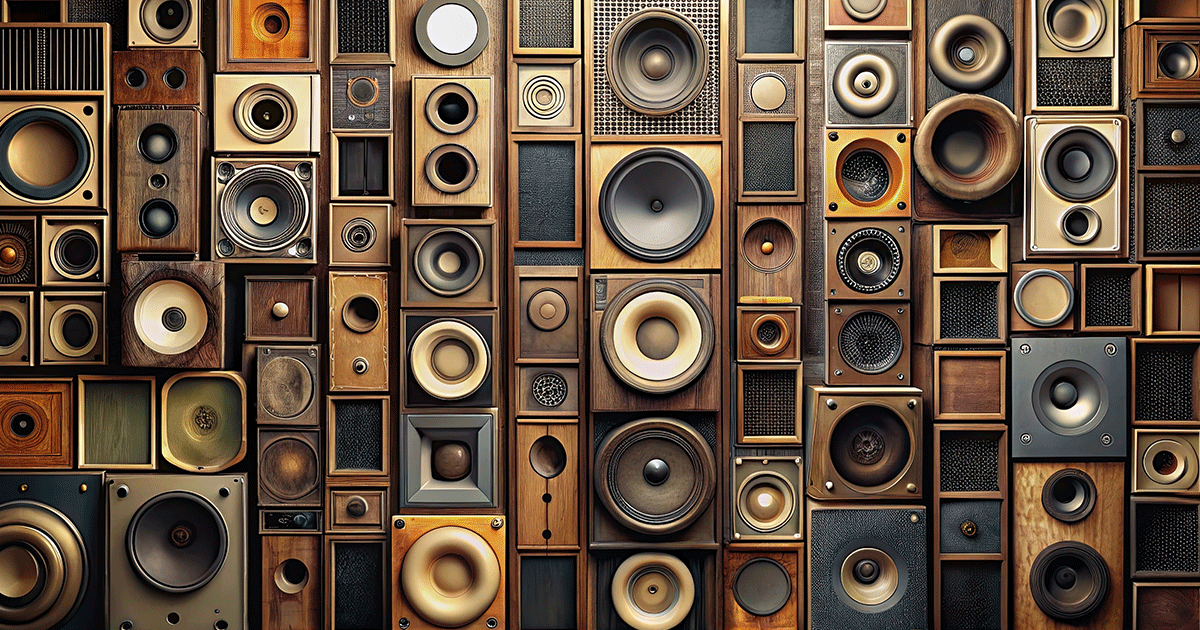

![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/spn/images/related_qa/c205_3_thumbnail_img_sm.png)















お礼
ありがとうございました。