具体的な病名は素人であるわれわれができることではありません。
が、これらの症状は自分の力でどうにもできない以上は専門家に相談するしかありません。
心療内科でも精神科でも基本は問診です。
心の動きをできるだけ正確に伝えるのが肝心です。
「○○な出来事に対して一気に体がだるい感じがした」
とか、寝る前に高ぶって眠れない日がしばしばある
といった細かい情報を分析した上で医者はようやっと病気の正体を
見抜き、対策します。
もし医者に行った場合の想像くらいはできます。
3番目、4番目、5番目にあげられている症状は効くまでに二週間くらいかかる薬で対抗します。何を見ても聞いても否定的な考えになりづらくする・・・前向きな気分になりやすくするベースとなる薬です。
特に5番の状態に対しては即座に対応するための薬が存在します。
涙が出るほど辛いものでなくても対応しますから、この対策は確実に取られますね。
4と6についてはカウンセリングを受けることになると思います。
カウンセリングもまた、対話による治療ですが、カウセリングの時は
心の状態次第では、かなり痛い話が出てきたりします。
最後の二つは肉体的なものですね。
体が防衛反応を起こしているんです。
病は気からの気がまさにやられて本当に体に影響が出ているという
わけです。
結論としてはすみやかに相談し、対策を取る必要があるといえます。
できれば家族の理解を得て、必要に応じて休職さえも視野に入れる必要があります。
私自身飼われている身ですが、何とか社会復帰できるように薬を調整したり(医者と相談の上)、治療法を模索したりしている状態です。
市販の安定剤は確かにあんまり良くないですね。薬はできるだけスマートにまとめた方がいいでしょう。
この手の話の場合は病気と言っても気持ちの問題だけに「気合や根性の問題じゃねぇか?」という考えが本人にもあるくらいなので、まずは病気と思わず、医者と思わず単純に
「精神的に痛いことが多いから、精神のケアにめっぽう強い専門家に相談する」という気構えでいいと思います。
先ほどの想像といっても自分自身もそうですし、ほとんどの人が同じようなものです。
心療内科も精神科も「医者」はあくまで肉体的な対処(脳も含めて)と治療するための具体案の指導がメインです。
最後に診察を受けるにあたり、できるだけ等身大に現状を語るようにしてください。医者には守秘義務というものがありますので、たとえばの話、「未成年でありながら酒がないとアイデンティティーが保てない」と話しても通報されることもなければ家族にも一切語られることはありません。この場合は「薬物依存」という症状として、入院を勧められるかもしれませんね。
今のは極端な例ですが、ようは秘密は守ってくれると言うことです。
それを踏まえていろんな話をするといいでしょう。





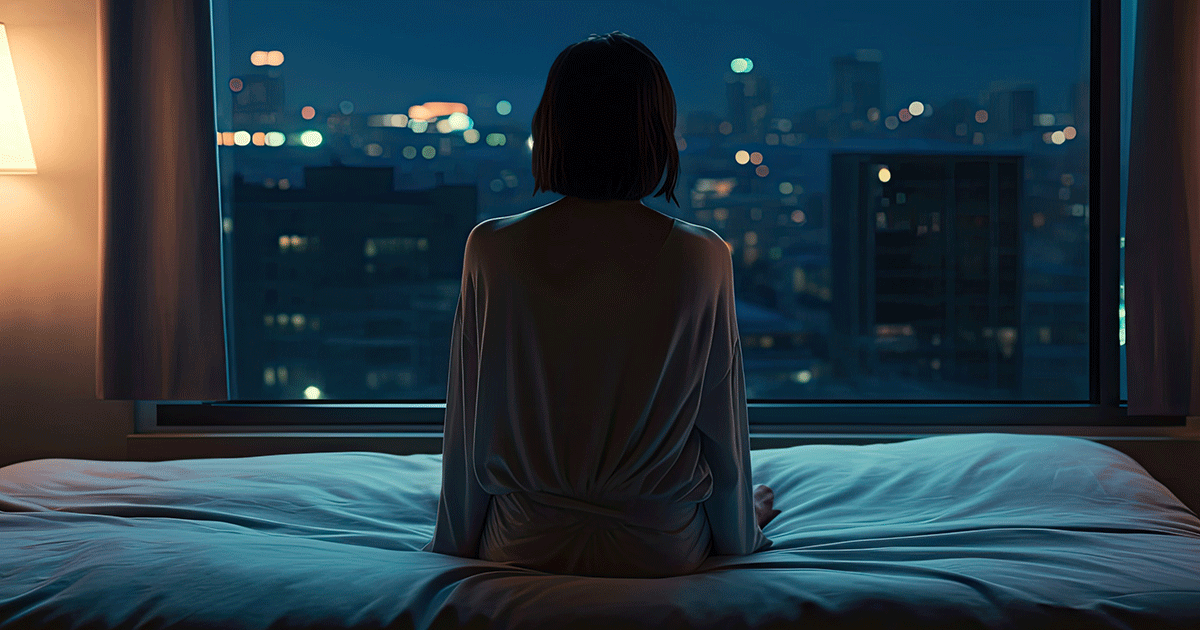


















補足
回答ありがとうございました。今まで『心療内科に行く=自分が心の病気だと認める』のが怖くて避けていましたが、最近真剣に辛くなってきたので…通院も考えなくてはと思います。 もう一つ聞きたいんですが、心療内科ではどんなことをするんですか?