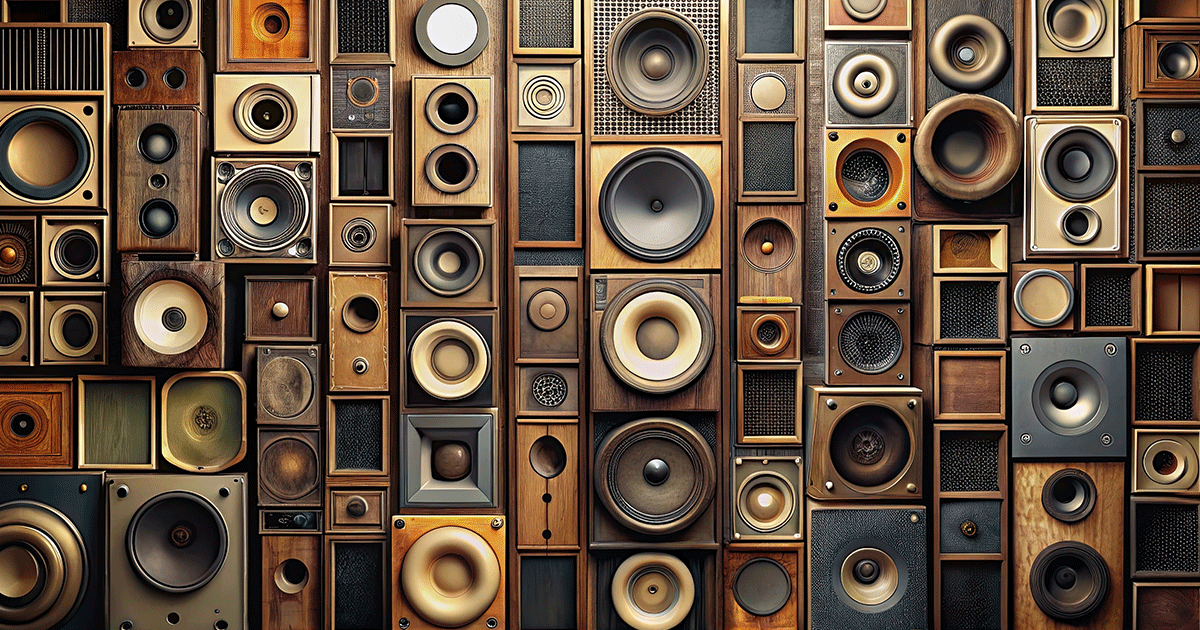はじめまして♪
2年前に母校の吹奏楽部の顧問先生からも似た様な話題が出ました(苦笑)
小中学の音楽担当の先生が案外この手の科学が解らなかったりするのでしょうか?
糸電話で音声が振動とは大抵理解してます。その後周波数とかで教育するためなのか、いろんな振動を忘れてしまうみたいですね。
いろいろな音声振動の複合された振動を記録しています。 糸電話でも男声の「あ~」と女声の「アー」はわかりますよね♪
いろいろな音で出来た音楽の全てを合成した振動が記録されているんです。
ケータイのスピーカーも それぞれの合成された振動を伝えていて、それを「人の声」「音楽」と 聞いている人間が経験上理解しているってことですね♪
理論的にと言われていますが、ここのサイトを見ている一般の人にもわかりやすく表現しますね♪
もしも 男声も女声も同じ歌を同じ音程で唱ったら、全く同じですか? 違いますよね。 テレビ等で「声紋」って聞いたりした事ありませんか? 「あ」「ア!」「あァ~?」と発音しても 基本の音程が違っても 倍音系列で本人がわかってしまいます。 この録音もマイクから電気信号としてアナログな電圧変化ですね。それを機械的な「溝」に記録したのが「アナログレコード」です。
さらに アナログレコードでは「溝」を V 型に刻んでいて、V字の白湯の壁で違う信号を刻むと言う 高度なアナログ技術が使われています。 しかも 大太鼓では「ブルブル震える」と「鉄琴ではウルサいけれど指で触ると感じない程の震え」を 一定の幅の溝に刻んで(エンコード)、それを再生するため正常に聞こえる(デコード)しています。 アナログレコードの場合は エンコード=イコライジング デコード=イコライザー と言うそうです。
最近は 中学校や高校の数学担当の先生に「なんで 1+1は2なんですか?」と聴くと、、 とか 科学の先生に「ゼロ」って どうやって決めたんですか なんて 、、
でも 大人に対する答えじゃなくていいから 子供にはそれなりに答えてほしいですね。
あ、話題が違いましたね、ごめんなさい。