一般的にガラスレンズは下記の工程によって作られます。
溶解→加工→荒ずり→砂かけ→研磨→洗浄→芯とり→コーディング
▼溶解と加工
高性能のレンズを作るためには、まず均質な光学ガラスが必要です。光学ガラスの種類は200種類以上、原料の種類は約70種類あります。それらの原料を目的の光学ガラスに応じて調合します。
調合された原料はまず石英るつぼで1次溶解され原料ガラスとなります。次に原料ガラスを白金るつぼに入れて本溶解を行います。1200~1500℃に加熱して溶かし、均質になるように攪拌していきます。溶解が終わったら半月ぐらいかけてゆっくりと冷却していきます。光学ガラスは板状の塊として取り出されますが、気泡や脈理(ムラ)などが含まれていないかどうか検査を行い、均質な部分だけを取り出してレンズの材料とします。取り出されたガラスは適当な大きさに加工され、円盤状のガラス板となります。
▼荒ずりと砂かけ
円盤状のガラス板の表面をレンズの形にしていきます。荒ずりではカーブジェネレーターという機械が使われ、人工ダイアモンドの砥石で削ります。レンズの曲率は砥石の角度によって決まります。荒ずりが終わるとレンズの形をしたガラスができあがり、続いて砂かけが行われます。レンズの表面を砂や人工ダイヤモンドの小さな球状の粒で磨き滑らかにしていきます。これらの作業でレンズは仕上げ寸法に近い形となります。レンズはまだ透明ではなく磨りガラスです。
▼研磨・洗浄・芯とり
研磨剤を使ってレンズの表面を精巧に磨いていきます。研磨はレンズの行程の中でも、最も重要です。研磨が終わるとレンズが透明となります。できあがったレンズは研磨剤などの汚れを取り除くため洗浄されます。研磨の終わったレンズは、中心を挟み込んで高速で回転しながら、光軸がレンズの中心となるように外周が削られます。下記のような感じです。
┫0┣ ←回転軸
■←砥石
▼コーディング
光の反射を抑えるためにレンズの表面に薄い膜を付けます。光の反射があると、レンズの光の透過度が落ちたり、反射光で余計な像ができるなどの問題が起こります。コーティングは真空装置の中で、コーディング材料を蒸発させてレンズ表面に膜を形成させる真空蒸着という方法が使われています。
専門書ほど詳しくありませんが、「図解入門 よくわかるレンズの基本と仕組み(秀和システム)」に上記が比較的わかりやす解説されています。レンズの基本も高校物理のレベルで理解できると思います。













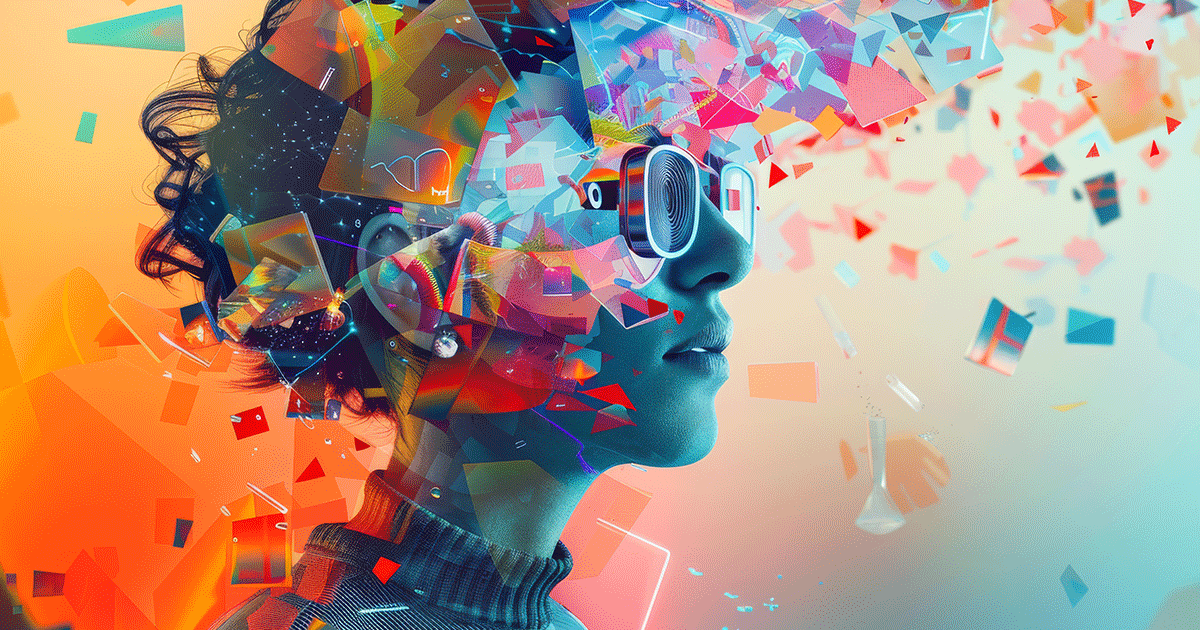
![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/spn/images/related_qa/c205_1_thumbnail_img_sm.png)

















お礼
分かりやすい説明ありがとうございます。
補足
芯取り作業ですがレンズ面の中心部分を押さえて(挟み込んで)回転させながら外周を削るということですが、押さえる(固定させる)ところがレンズの形状から少なくなり削るのに安定しないような気がします。何らかの工夫で固定させているのだと思うのですが、その固定方法をお知りでしたら回答いただきたいと思います。