Q/CPUっていろいろ種類がありますが何が違うんでしょうか?
A/そうですね。設計思想が異なるというのがCPUの種類の違いですね。大別すると単純命令処理を一度に大量に処理するプロセッサと、複雑な命令処理を一つ一つこなすタイプがありますね。また、技術的にベクトル型(NECが有名)とスカラ型などのプロセッサの違いもありますね。それぞれに使われる目的に、性能、コスト、製造、利点などが異なります。
ちなみに現在、市場で使われるCPUの主な物は、インテル社やAMD社、VIA社がパーソナルコンピュータに使うx86互換プロセッサ。(詳しくは後述)
Appleコンピュータのマッキントッシュに使われるFreescale社のPowerPCおよびIBMのPowerXシリーズ(Xは世代数字)と呼ばれるPower系プロセッサ。(次世代ゲーム機は3社ともPowerを採用、そのうちマ社のX-BOX360は既に製品化済み)
インテル、HP社が協同開発したIA-64。サーバー向け64bitでx86とは全く異なる技術となるVLIWベース。
SUN Microsystemsが開発したサーバ向けSPARC。ARM社が開発したARM系(情報家電に使われる)やインテル社のXScaleなどがある。
それぞれ基本構造が異なり、処理する手順が違うためそれぞれのプロセッサで扱えるプログラミング命令の種類が異なります。
Windowsを搭載したパソコンの場合は、その中でもx86互換のプロセッサが使われます。CISC系であるx86は1978年に登場したi8086というプロセッサを基幹技術として発展させたプロセッサで、製品の処理精度を16bit→32bit→64bitまでの3世代に渡って更新しているプロセッサです。これだけの歴史があれば、基本的な構造を維持していても構造をわずかに変更した派生品が出せるようになります。そこで開発元のインテル社以外にもAMDやVIAといった会社が互換のプロセッサを開発し、64bitのx86-64(通称x64)はAMDが最初に開発しました。
さて、この3つのメーカーのプロセッサの違いは何かというと、x86の基本設計は維持しつつ、細かな改造が違うのですよ。そのため、周波数、発熱、消費電力、性能がわずかずつ変わってくるのです。
その中身が、どう違うかと言うことになると自動車のエンジンが違えば燃費や加速、車の車体の大きさが違うというのが何となく分かるのと同じで、多くの場合は専門用語が多く分からないでしょう。
Q/動作周波数○○GHzってどういう意味でしょうか?
A/Gはギガ(10億を意味する単位)、Hzはヘルツです。ヘルツはきっと中学校ぐらいで電気を習う際に習うはず。電流の振幅を指します。
この振幅が何を意味するかというと情報を何回お隣の回路から受け取っているかが分かるのです。1GHzなら毎秒10億回データを隣の回路から受け取れるということになる。まあ、これは波に浮かべた船が波に乗って前に進むのと同じだと思ってください。振幅が多ければ、運ばれてくる情報を乗せた船が1秒当たりで10億隻あるということになります。
同じ名前、同じ構造のプロセッサならば、1億回のデータ転送より10億回の方がより多くの情報を理論的には処理できることになりますから、速くなるのです。
ちなみに、同じプロセッサなら速くなりますが異なるプロセッサならそうとも限りません。それは単位データが同じとは限らないためです。これは4人乗りのボート1隻(単位データ)で80人を1時間に4往復(4Hzと仮定)で運ぶのと、1隻で8人載りのボート(単位データ)に1時間で3往復(3Hzと仮定)で運ぶ場合にどちらが速いのかというのを考えれば分かります。一度に積載するデータ量によって速度が変化します。また、これは処理が確実に完了すると保証された数字ではなくあくまでやれば出来るというだけです。そのため、途中で沈む回数はこれに含まれないということも理解しなければいけません。
よって、同じCPU同士で比較すると周波数が高いほど高速だが、異なるCPUと比べると周波数が高ければ低い周波数より高速とは限らないということになります。





![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/spn/images/related_qa/c205_4_thumbnail_img_sm.png)






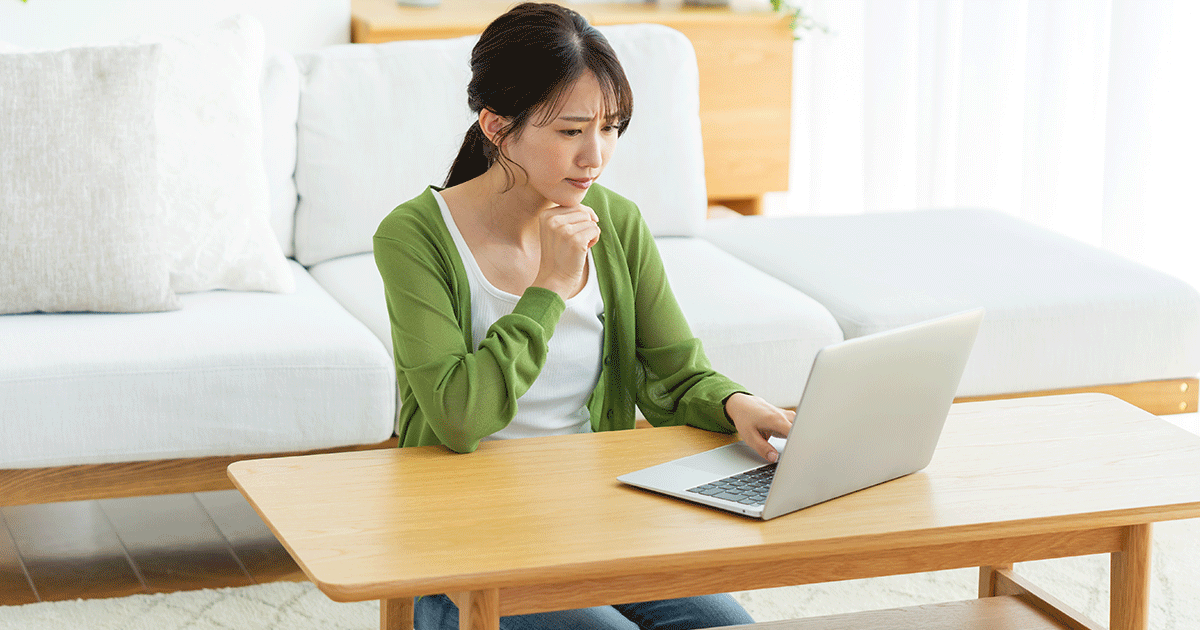















お礼
後半部の周波数について(他社では比較できない等)参考になることばかりでした。ありがとうございます。