>初心者でも分かる様に
仕組みは非常に単純ですが、
理解できるかはどのレベルの初心者か次第です。
M2,M3で1つのインバータ
M4,M5で1つのインバータを構成するのは理解できますか?
理解できない場合は、まず論理回路のインバータというものを調べてください。
次に、インバータの入出力が互いに接続されていますので、
何も変化が無ければデータが保持されます。
これがラッチ回路(メモリセルの本体)です。
M1とM6はトランスミッションゲートと呼ばれるもので
メモリセルにデータ線のデータを書き込んだり、
メモリセルからデータをデータ線に読み出すためのものです。
今、点AがH(3V)、点BがL(0V)としましょう。
データを読み出すためには、
まずビット線1、2を1.5VぐらいのHとLとの中間ぐらいの同じ電圧にしておきます。
これは読み出しを高速にするための技術で、ビット線のイコライズとプリチャージと呼ばれます。
その後ワード線の電位を変化させて、FET M1M6をオンにします。
ラッチ回路の能力が有る程度あれば(それが大前提)、
そのビット線の電圧は接続された点A,点Bの電圧に一致するよう変化します。
結果として、ビット線1、2の電圧はメモリセルの内容に応じた値となり、それをビット線に接続されたセンスアンプで検出し、メモリICの外に出力します。
次に書き込みですが
先ほどと同じメモリセルの内容は先ほどと同じであるとして
まずビット線1,2の電圧を書き込みたい電圧にします。
ビット線1をL、ビット線2をHとしましょう。
この状態でM1,M6とをオンにすると
ビット線と、点A,Bとの電位が一致しないのですが、
この時、ビット線に電流を供給する回路の能力が
メモリセルのインバータを構成するFETの能力よりも高ければ(それが大前提)、
点Aの電位はHからLに、
点Bの電位はLからHに
強制的に反転させられます。
これが書き込みの原理です。
もしインバータを構成するFETの能力が高すぎると、メモリセルのデータがビット線のデータと一致するように変化しなくなります。
昭和50年代のSRAM関連の特許を探せばいくらでも解説されていますが、
一般人には探すのは難しいでしょう。














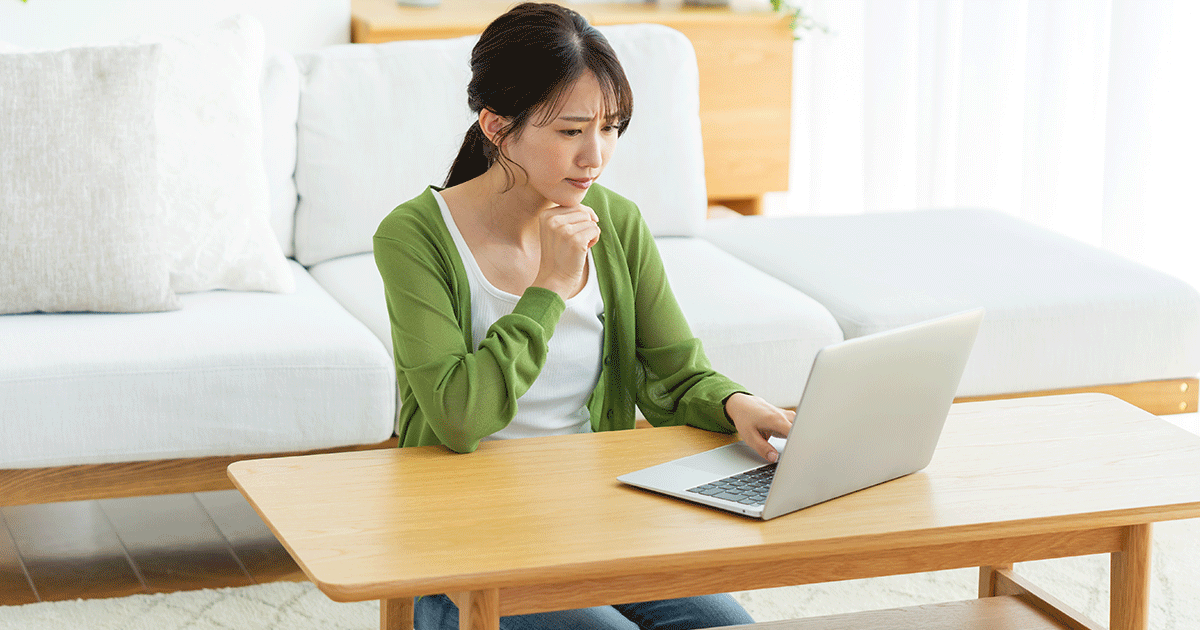


















お礼
詳しい説明ありがとうございます。全てを理解は出来ませんでしたが、理解が進んだと思います。