文明度に応じた社会観の差によるものだろうと思います。
集団生活する動物は元来血のつながりをベースに血縁社会をつくり、その共同体の中で保護されて一生を終えます。人類がそんな進化段階にあったとき、広大な土地のあちこちにそんな血縁社会が宇宙空間に浮かぶ星のように点在し、各星の住民間では食うか食われるかの争いがメインを占めますが、中には友好的な関係を築いたものもあったでしょう。いずれにせよ、自分の属す社会の外はジャングルというのが、人類の永い歴史の中でDNAに刷り込まれた意識ではないでしょうか。
そんな血縁社会が、より大きなメリットを自覚して別の血縁社会と融合したり、天災人災で住んでいたスペースを失って人間の移動が起こったりして、血のつながりを超えた地縁社会が生まれるようになります。それらの社会レベルに共通して言えるのは、社会構成員が互いに顔見知りであり、素性を知っているということで、素性がはっきりしているか否かがその社会の境界線になります。つまり社会のウチとソトという観念です。
社会というものの定義を、その構成員が相互の利益を目標にしてひとつの時空を共有し、互いに一体感を感じている生活共同体であるとするなら、上で述べたのは社会空間が拡大して境界線が広がっていっているという現象なのです。
歴史を見ると、最初は宇宙空間に小さな社会が星のように点在している状況の中で、何らかの理由で限られた広さのエリアに外から大勢のひとが集まって人口密集地域が生まれ、それが都市と呼ばれるものになり、そして都市で文明が花開きました。そのような都市では、そうでない地域(田舎と呼ぶことにします)に存在していた社会秩序はそのまま移植することができません。雑多な小社会から来たひとびとが巨大社会を形成する必要に迫られるわけです。その巨大な機構を動かすために、田舎にはなかったもっと合理的な社会メカニズムが作られ、新たな秩序が生まれていくのです。都市文明というものが生み出したのがそれです。
このような都市は、人類学的に同じ民族の中で生まれたものもあれば、異民族まで包含する規模のものもありました。長安やバグダード、イスタンブールやパリなど、それぞれの時代の文明の最先端にあった都市はそんな国際都市の典型です。
だから都市には高い文明があり、田舎は低い文明(別の言葉では野蛮。文明と野蛮は対義語であり、われわれは文明⇔野蛮を両極とするスケールを用いることができます。わたしが文明度と言っているのは、そのスケール上の目盛のことです。)の中にいるということが言え、つまり「都会は進んでおり、田舎は遅れている」という観念の基盤をそこに見出すことができるのです。
社会の話にもどって、都市住民にとっての社会(上の定義を思い出してください)というのは、自分のまったく見知らぬ他人、ひょっとしたら一生涯出会うことすらない他人と共存協働する社会であり、顔見知りであるか否かという社会観の持ち込めない場になっています。必然的にライフスタイルはそういう形に方向づけられ、社会構成員個々の精神姿勢は田舎のひととまったく異なるレベルに置かれます。
これが冒頭の文明度に応じた社会観の差ということの内容です。
現代グローバル社会では、情報通信の空間的広がりと内容のち密さの深まりが同時に進行しており、われわれは世界そして宇宙という巨大空間に対する詳細な認識を持つようになってきています。だから最先端文明に浸っているひとびとは、世界中の人間に対して時空を共有し、同じ人間同士という一体感を持つに至っているわけです。日本にいるひとがアフリカの飢餓難民に一体感を抱いている。現代ヒューマニズムの理想の一例でしょう。世界はそういう方向に向かって、間違いなく進んでいるとわたしは思っています。ただし人間個々人の持つ社会観世界観は自分が日々暮らしているミクロな生活共同体の中の価値観に引きずられてそう簡単には変化しません。しかし何代もの世代交代を経て着実に進化していることは歴史が物語っていると思います。それが太古から連綿と続けられてきたこの世界の姿です。
もうひとつ付け加えておきたいのは、文明度という点で都会にも劣悪な人間がいるし、田舎にも都会の平均を上回るひとがいます。都会の劣悪な人間が、自分は都会人だからと田舎の人間を見下すことは枚挙にいとまありません。
そのような人間は具体的な人間のクオリティを評価する能力を自分の中に養成しておらず、「都会は先進、田舎は後進」というラベル思考を行っているだけであり、本質的な価値の認識がそこには欠如しています。そもそも評価対象として都会と田舎というディコトミーを用いること自体が、都市文明の中にはぐくまれた、「より広範な人類共同体への指向・社会的一体感」を否定しているわけで、そのようなひとが文明⇔野蛮スケールのどこに位置するかはおのずと明らかでしょう。












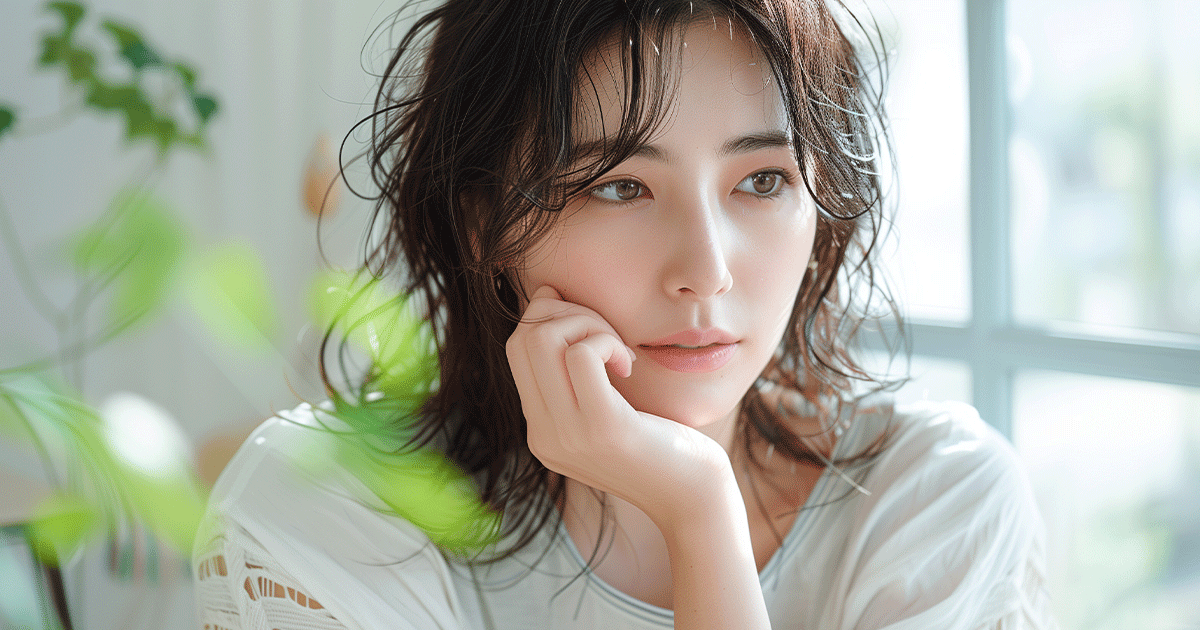

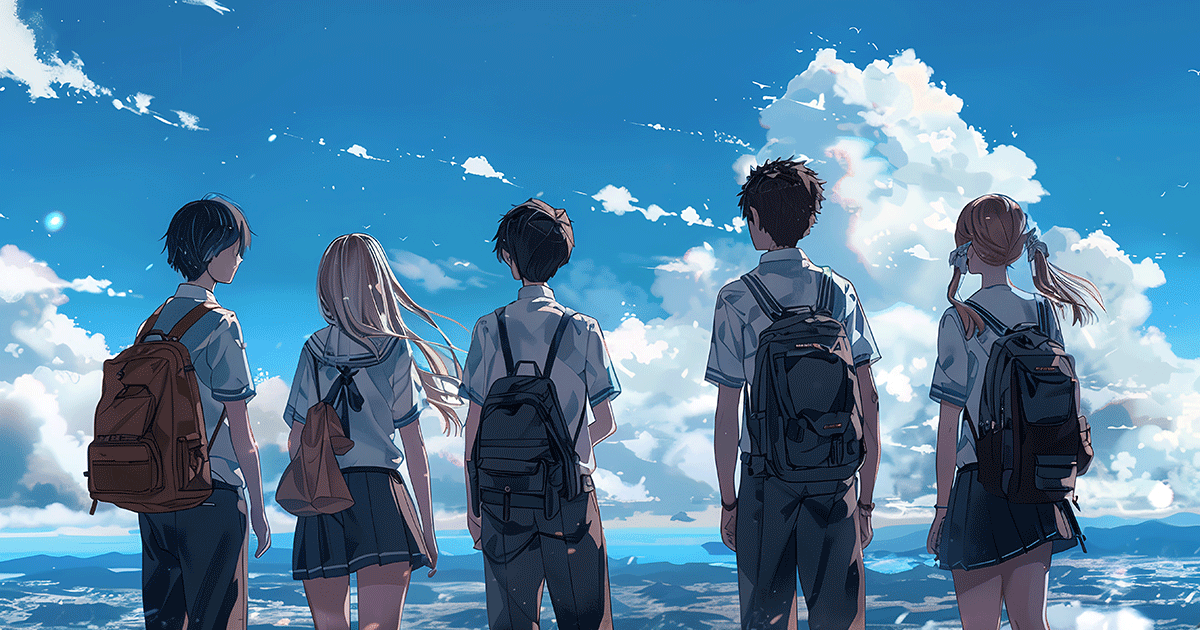








お礼
自分は正社員でしたが、下手下手に出てました。 パートのおばちゃんの顔色をうかがい、パートのおじちゃんには怒鳴られてました。 余っている家をあげるとの話も有りましたが、絶対要らないと思ったほどです。