>なるほど・・・。衿先が出ているのは絶対おかしいというわけではないのでしょうか。
【絶対おかしいというわけ・・】ではなく、見えているのがホントということなのですが、いまどきの人は、これを余分とおもうから変だという感覚ですよね。
大島だから、紬だからそれでもおかしくないということではないのです。
本来、寸法的には1-2寸は見せる?がホント。
逆に襟下寸法を長くすることで襟分を節約(襟を短くする)するということもありだから見方です。
>足し布をして身丈を伸ばすことになっても、おはしょりで隠れる部分だったら良いと思うので、仕立て上がったらそれを着て堂々と出かけたいと思います。
これもね、身丈を別布で伸ばすというのは、
オハショリ(2重折の下の部分という意味でしょう?)で隠すのではなく、
帯下に隠れる分量(伊達締めのあたり)なので
4寸までが限界ですが、別布で身丈を出す。
ただし4寸以上(16cmぐらい?)は足し分が見えます。
ただし襟先に関しては、左の襟先(上前)はおなじにして、
下前(右の襟先)は別布という作業にしますから、
元の襟が上前・左寄せ?になって、
不足分をそっくり下前(右襟先)に足して仕上げます。
途中で切って、両サイドちゃんとみえるようにしないこともないですが、
なるべくはさみは入れないのが鉄則ですから。
きてしまえばわからないところは、着物というのは相当にあれこれ
按配して結構、「秘密」に作ってあるものなんです、ムカシはね。
デ、あえてみえる上前の襟先に余分な襟を見せて、ちゃんと見える部分を気取るのが目的かもしれないです。
あれが見えないと、襟分もなくて・・・ということなのかな昔は逆にね。
私は、和裁が趣味なおばちゃんです。
古い着物をターックサン解いてます。
昔の人の知恵がわかって面白いですよ。
今のセンスで着物を見ると、おかしいかもしれないですが、
着物は将来的なリサイクルを基本として着るものなので、長くあるところは
そのままとっておく、そして、余裕としてみせる・・・という考えなんです。








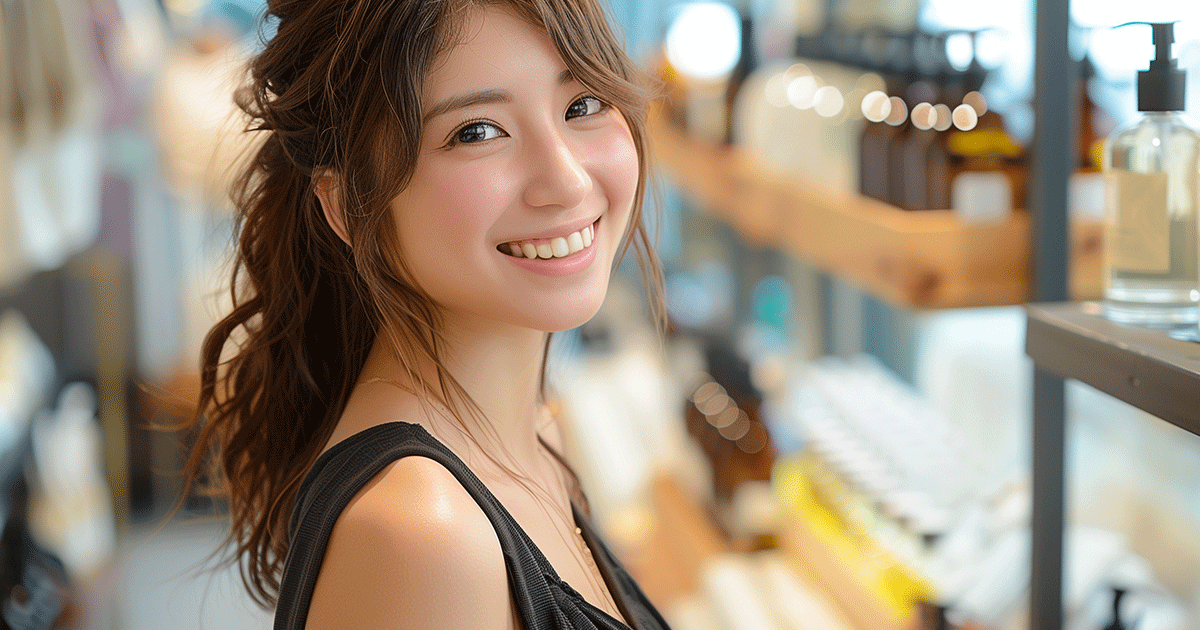
















お礼
なるほど・・・。いろいろ勉強になります。 高校の時に家庭科の授業で浴衣を縫ったのですが、浴衣を含めて着物の仕組みはすっかり忘れてしまいました(笑)。 改めて勉強すると楽しいですね。 ありがとうございます。