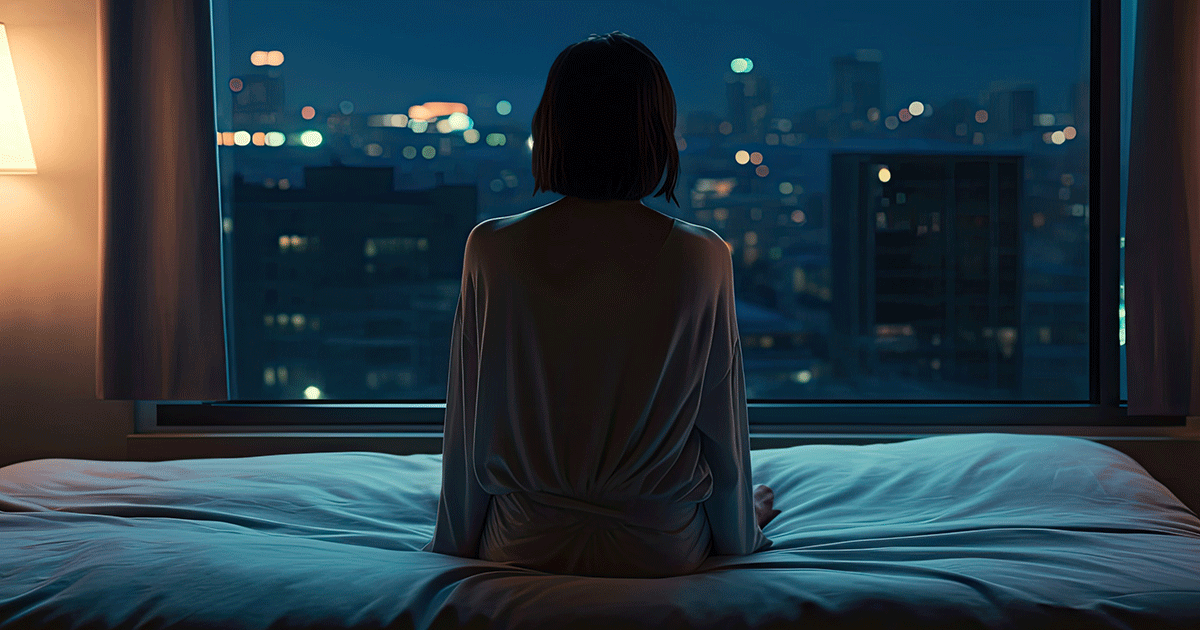看護学生という立場からお答えしますと・・・
まず体温を測るときは大体10分測定すればより正確な温度になるといわれているのはご存じですか?
電子体温計は基本的に『予測値』と『平衡温(実測値)』の二つが測定出来るようになっています。
『予測値』というのは体温計をこのまま10分間同じ姿勢で同じ場所で測り続けたとして、10分後にはどれくらいの体温になるかを体温計が自動的に計算して出した値、つまり体温計の『予測値』なんです。
これは体温計によっても違いますが、大体30秒~1分程度で出るようになっています。
普段私達が『体温』と呼んでいるのはこの『予測値』の場合が多いです。
『実測値』が測れることを知らない方も多いですよね☆
では『実測値』は、というと読んで字のごとく本当に10分程度測ったときの値です。
ですから、正確に体温を測るにはこの『実測値』を出した方が本当は良いのです。
とは言っても今の体温計は精巧に出来ているので、そんなには『予測値』と『実測値』の差は出ないので普段測る分には『予測値』で充分だそうです(と先生が言っていました^^;)。
なお「二度目の測定でも確定できない」のは、私の考える限りでは測り方に少し工夫をすればいいのではないかな~と思います。
yokyoさんが舌下(舌の下)で測っているのか脇の下で測っているのかが不明なので詳しいことが言えませんが、例えば脇の下であれば
・発汗(→汗は必ず拭き取る。そのときはこすらず押さえて汗をとる)
・体温計を挟む位置(→脇の下に一番深く窪んでいるところに身体に対して約45度の角度をつけて挟む)
と言った工夫で大分改善されるのではないかと思います。
舌下であれば、
・口の中央から斜めに入れる
・測定中は鼻で呼吸をする(→まあ口では呼吸できないと思いますけど^^;)
と言った工夫をしてみてはいかがでしょうか?
長くなってしまいましたが、とりあえず一番早いのは体温計に添付されている注意書き(?)を読むことだと思います。
それを読んでみてはどうでしょうか。
かなり端折った説明になってしまったので分かりにくかったらごめんなさい!
とりあえず私の知識の中から説明してみました☆