- ベストアンサー
直交変調について
テレビのケーブルについて勉強中ですがS端子の説明でわからない 表現がありました。 「色信号は本格的なコンポーネント映像信号のようにCb/Crなどに分離したものではなく、両者を直交変調した形態である。」 という文章ですがこの”直交変調”という言葉の意味が色々調べましたが分かりません。 上記の文章をわかりやすく解説して頂けないでしょうか・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- Nobu-W
- ベストアンサー率39% (724/1831)
回答No.1













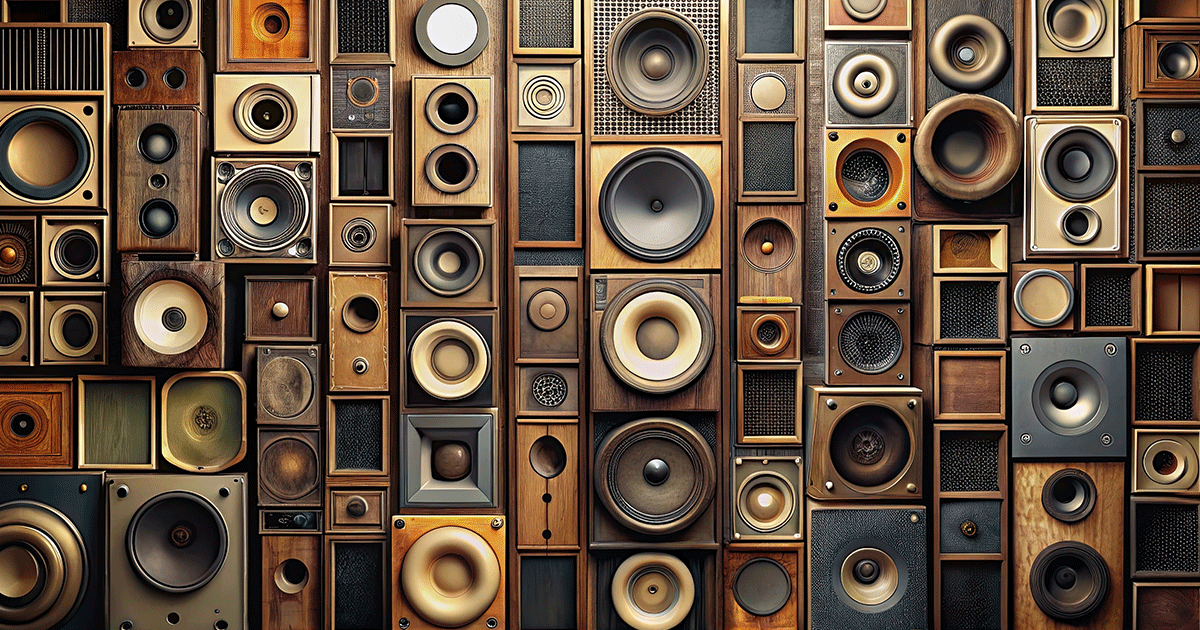
















お礼
「一定の規格にそって高い利便性を確保しませんと、困った事になりますので、幾つかの規格が造られたのです。」 →ちゃんと経緯があって結果があるのですね・・。 「Cb/Crの混合ですが、”直交変調”という表現は、残念ながら私も見覚えが無く、後から分離可能な状態での混合=ミックス と理解していました。(まぁ、分離出来なく成らないよう、なんらかの工夫として「変調」などの技術が関わっていると考えて良いと思います。)」 →結論はこういう事なんですね・・。 「色差って、簡単に言えば、白黒用の輝度信号に対して、光の3原色の1つを引き算する信号で、本来の色と他の2色の信号量も割り出せます。もう一色の差信号があれば、2色めの信号と、もう1つのこった最後の3色目の信号も割り出せます。これが「テレビ用の信号」として、白黒テレビ放送時代からの互換性を持たせた手法です。」 →当然知りませんでした。 「乱暴なSからRCA」変換ケーブル自作をした経験が在ります。 →行動に移せる人でないと深い理解はできない・・・。勉強になりました。 有難うございました。