No.2の回答にもう少し付言するなら、「ないはずの音が出る」の代表例は高次歪みです。
たとえば、1000Hzの信号を入力したとき、それ以外の音波を発生しないのが理想的ですが、現実には2000Hz、3000Hz、4000Hz...といった音波も出てしまいます。ウーファーで特に問題になるのは4次~5次くらいの共振で、たとえばいわゆる「低音」である200Hzを入力したとき、5次の1000Hzの音が出てしまうと、いわゆる「高音」が聞こえることになります。人間の耳は、10000Hzくらいまでの音を敏感に感じ取るので、ウーファーの高次歪みは非常に大きな問題です。
この歪み率は、一般的なデータシートには記載されていませんが(記載しているメーカーもある)、PCを使って比較的簡単に調べることができます。サイン波を入力してマイクで収音し、周波数特性を見れば、だいたいのところが分かります。もしマイクがなくても、ウーファー単体でたとえば100Hzのサイン波を鳴らして聴き比べれば、ものによってかなり聞こえ方が違うのが分かるはずです(なので、データシートの「周波数特性図」だけを頼りにしても、本当の音の良さは分かりません。より正確には、高次歪みが増えない範囲でハイカットし、ツイーターに任せるか、ツイーターがそこまで低い周波数での使用に耐えないならミッドレンジを追加する、ということになります)。
「あるはずの音が出ない」の例としては、過渡特性の良し悪しが挙げられます。
過渡特性というのは、俗にいう「立ち上がり・立ち下がり(変な日本語ですが)」のことで、ある信号を入力したときに正常に反応を始めるまでの時間と、信号がなくなってから完全に無音になるまでの時間の中での経過の様子、です。
たとえば、100Hzの音波を8サイクルだけスピーカーに入力したとき(このような信号をトーンバースト信号という)、本来なら最初から正確な波形が観察されなければなりません。また、波形は8つで収束し、直ちに無音にならなければなりません。
しかし、現実には最初の2~3つは不完全な形だったり、8つ目以降にもビロビロ~と波形が続きます。これは、立ち上がりに追随できていない、勝手に振動し続けている、ということを意味します。
当然のことながら、使いたい周波数帯域内において高次歪みが小さく、過渡特性の良いウーファーの方が良い(理想型に近い)ウーファーです。より正確に再生でき、不要な音によって本来の音をマスクしてしまわない方が、客観的には「情報量」が多いといえるでしょう。
しかし、あまり歪み率が低くはなさそうなドライバーを使っているにもかかわらず、「このスピーカーは情報量が多い」といった評価をしているケースも見かけます。多少の歪みがあった方がメリハリや押しの強さを感じることもあるので、必ずしも科学的なデータと好み・聴感は一致しない、ということです。











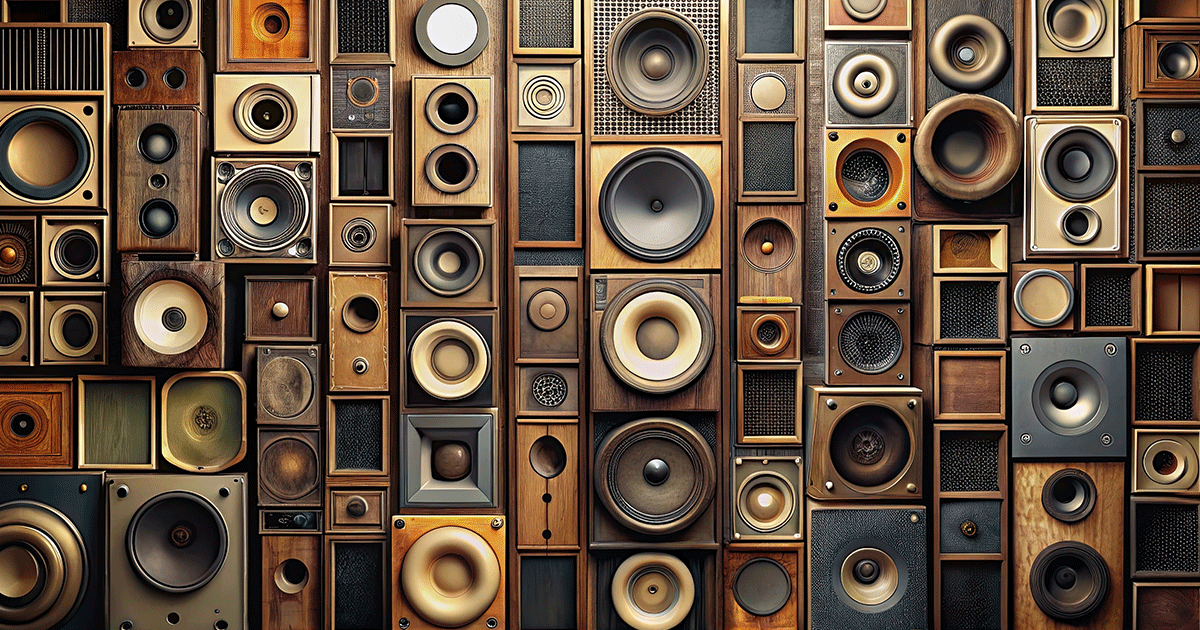















お礼
たいへん参考になりました。ありがとうございました。