他の方の回答が部分的に間違っていますので正解を書きます。
UDMAもUATAも表現の仕方が違うだけで云いたいコトは同じです。
要はATA(IDE)規格のHDDというコトで、かつUltra DMA転送に対応しているというコトです。
大昔はPIOといってHDDをCPU制御で動かしていましたが、現在はDMAコントローラという
専用のチップ(たいていはサウスチップに内蔵)で制御しCPUに負荷がかからないように
うまく処理しています。その結果、高速転送が可能になったのです。
ご質問の交換前・交換後のHDDの型番が不明ですが、今ですと
普通はUltra ATA/100(UDMA5)だと思います。回転数によっては
熱対策など必要になる場合もあります。普通は4200rpmか5400rpmです。
UATA/100=UDMA5です。普通のノートのHDDはコレです。
UATA/33=UDMA2です。普通のノートのDVDドライブなどはコレです。
UATA/UDMAの表現の仕方に関係なく、すべてはDMAコントローラの転送上限と
HDDの転送速度の上限でマッチングが決まります。
UATA/100対応サウスチップのパソコンにUATA/66のHDDをつけると、
HDDの本来の速度で動作しますし、逆にUATA/66が仕様上限のサウスチップ搭載パソコンに
UATA/100のHDDをつけても、本来の転送速度より若干落ちるというコトです。
同じATA(IDE)規格で2.5インチノート用のHDDでしたら物理的にも
論理的にも問題なく使用可能です。内蔵しているもの同士を交換したり、
外付けのケース(秋葉で\900くらい)に入れて手軽なUSB2.0ストレージに
利用したりもできます。
HDDの型番を補足いただければより正確な解答ができると思います。
型番はWindowsであればデバイスマネージャで判ります。







![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/spn/images/related_qa/c205_1_thumbnail_img_sm.png)

![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/spn/images/related_qa/c205_2_thumbnail_img_sm.png)
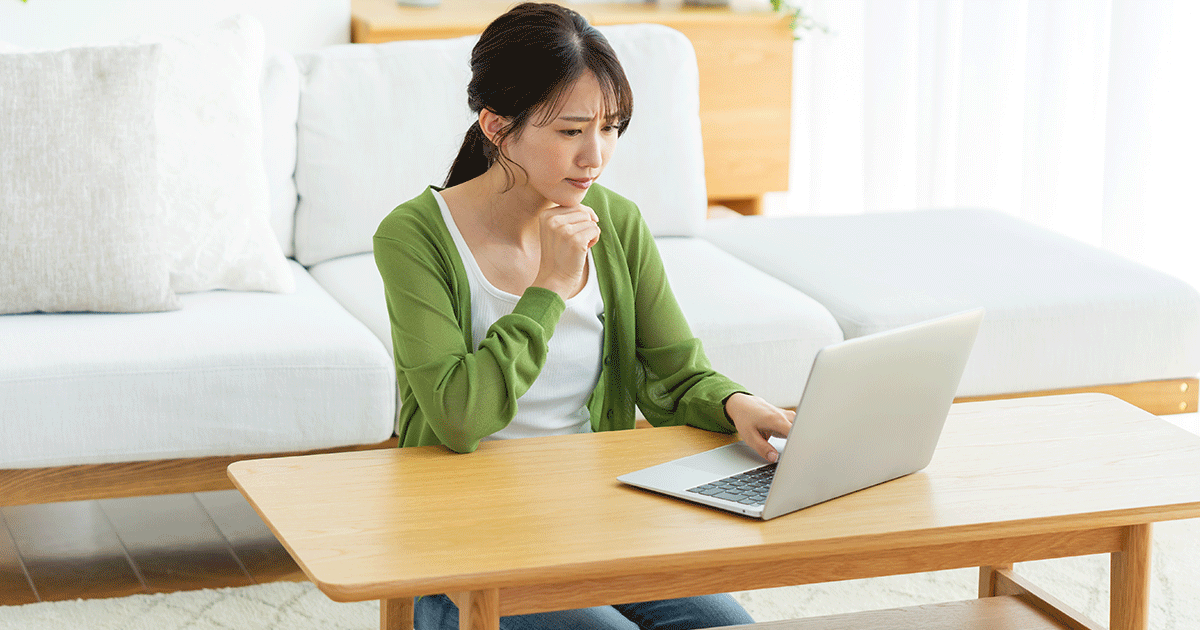














お礼
ありがとうございます。 やってみます。