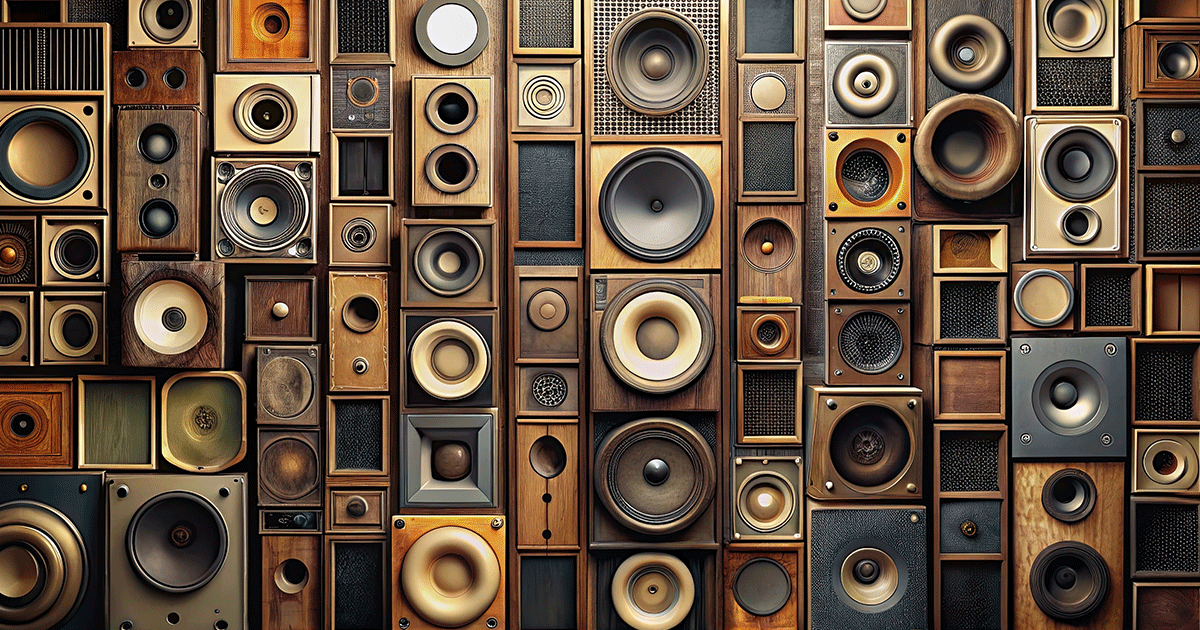- 締切済み
オーディオ環境について
お世話になります。よろしくお願いします CDを再生する時に、CDプレイヤーとアンプを光デジタルで接続するのと pcのDVDドライブでCDを読み込んでM/Bのオンボード光デジタル出力でアンプと接続 するのでは音が違うのでしょうか?私は0と1しかやり取りする情報が無い以上、 よっぽどピックアップが劣化していたりしない限りは違いが無いのではと思います
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ponpokona-
- ベストアンサー率40% (313/780)
回答No.7
- HAL2(@HALTWO)
- ベストアンサー率53% (2375/4446)
回答No.6
- ponpokona-
- ベストアンサー率40% (313/780)
回答No.5
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
回答No.4
- iBook 2001(@iBook-2001)
- ベストアンサー率48% (4211/8744)
回答No.3
- kita_s
- ベストアンサー率45% (630/1383)
回答No.2
- hibari2011
- ベストアンサー率21% (34/158)
回答No.1