- ベストアンサー
シャッター商店街の電気屋さん
私の町は神奈川の中の田舎で、シャッター通り商店街が多くあります。 その中に必ずと言ってあるのが、営業はしているけど売らない電機屋 です。ほかの業種は早々シャッターを閉め撤退し、2Fの住居部分のみに 明かりが灯るようなスタイルなんですが、電気屋さんは一応営業してます。 商品のラインナップは、ショウウインドー真中にカラーテレビ (ブラウン管でグレーマスクの昭和時代のものでキドカラーや 輝などの木目)、2層式洗濯機、エアコン(なぜか新型)蛍光ランプ (環状型の吊り照明)、シスコン(Lo-DブランドやVictorのCD-4など 一間分のサイズと金糸織のサランネットスピーカー)などです。 商品のラインナップからして、メーカー系チェーンストールなんですが このような営業形態はなぜ起こるのでしょうか? 閉店しないのは赤字経営の税金対策なんて聞きますが実際のところは どうなんでしょうか? 特に、メーカーはサービスや修理その他の切れた商品を陳列されても 問題はないのでしょうか?上記の商品に加え、看板にNationalなど 社名変更が決定したブランドや、日立マスタックスなど過去の製品名 を連ねた店名などメーカーの野放し状態はブランド維持にもマイナス な面があると思います。 私は、古い製品は哀愁があり、作りこみが丁寧などもあり物自体は あってもいいとおもいます。であれば、買い取り販売のものでも 再度メーカーが買い上げミュージアム化する(一例です)とかして 新商品をネットショップで売るのではなくそういうお店においてあげる とかしてあげれば回転率もあがると思います。話はそれますが、 いま無店舗販売が低コストで盛んですが、そういう売れる商品を持てず に経費をかけて店舗を維持しているお店があるということを忘れてま せんか? 知っている方はなんでもいいので、(追加疑問や補足可) また、お店の方、メーカーの営業の方誰でもかまいません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答








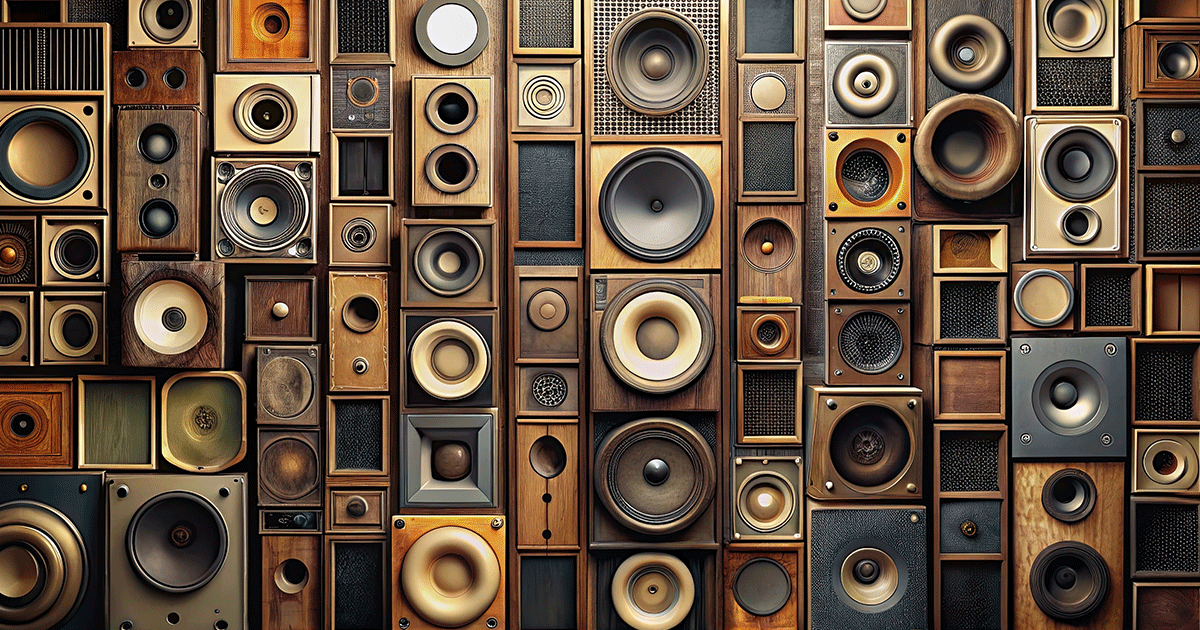




















お礼
ご返答ありがとうございます。 >電気屋さんの選別の仕事 こんな仕事あるんですね。確かにナショナルや日立を大手家電メーカー にしてあげたのはこういう町の電気屋さんなんですね。小さい頃は ナショナルなんかは「週末特選品フェア」などといって蛍光ランプを 買うと畜光プルストラップや色の変わるストローなどもらえて 一つの楽しみでした。最近は某大型店の影響で聞かなくなりました。 ただ、このままでは団塊以降の世代の終焉とともになくなってしまう 訳ですね。私の年代は大型店の名前しかでない方が多いと思います。 話は少しそれますが、私は自転車は地域のお店と決めてるのです。 パンクの修理とかで必ずお世話になるからです。しかし、最近の家電は 町の電気屋さんに修理を出しても単なる窓口としてしか機能しないので 旨みがなくそれも難しいのかも。(断られることが多い)